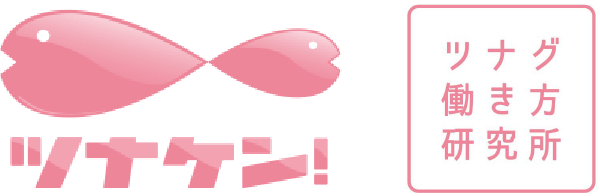【多様な働き方を研究するコラム】
退職者に「帰って来いよ!」アルムナイ制度のススメ!
アルムナイという言葉を聞いたことがありますか。
そもそも「アルムナイ(alumni)」とは、卒業生とか同窓生といった意味を表す英語です。これを学校から会社に置き換えて、「退職者」を指す言葉として使われるようになりました。
そして退職者と企業が繋がりを持つということをアルムナイ制度と言います。このアルムナイ制度が、空前の人手不足である昨今、話題になっているのです。もともとは、退職したOBにセールの案内をメルマガで送ったりするような取り組みからはじまったようです。
しかし、このやりとりから復職に至るケースが、けっこうあるのです。
別れてもLINEでつながってた元カレと元カノが元鞘に収まった――。
ベタにいうと、そういうことですが、人材業界的に解説すると、アルムナイ制度は「退職者のタレントプール」といえます。
タレントプールとは、優秀な人材を候補者として溜めておいて、コミュニケーションを取る続けることで採用に結び付けるという採用手法です。どうしてもやむを得ない事情で退職したスタッフのカムバックは、在職時の経験があるぶん、まさに即戦力採用と同じ効果があります。そういった意味では、退職者のプールは最も優秀な人材のプールともいえます。
このような解説をすると、なんだか御大層に聞こえるかもしれませんが、退職者と個人的にFacebookなどでつながっている従業員は少なくありませんよね。辞めた後も飲みに行ったり遊んだり。これも一種のアルムナイ制度です。しかし、しっかりと「公」として制度化していない場合、退職者側から「もう一度働きたい」とか「復帰させてください」とアプローチしてくるのは、相当ハードルが高いはずです。
だからこそ、企業や職場として制度化する「公」のアルムナイ制度が重要なのです。
空前の人手不足を背景に、アルムナイ制度には新しい採用ツールとしての期待が高まっています。しかし、この制度に対する個人的な思いはもっと別のところにあります。採用難のいま、人事戦略のトレンドは間違いなく「離職防止」です。そのため、いつ辞められるのかと、ビクビクしながらマネジメントしている現場管理職がいま、どれだけ多いことでしょうか。
また、超売り手市場のご時世とはいえ、辞めたら後がないからとギリギリまで我慢する働き手のほうが、いまだ多数派でしょう。ただでさえ人材流動性が低いとされる日本において、離職防止に行きすぎるのも、双方にとって不健全なのではと思うのです。
一回、辞めても戻ってこれる軽やかさと安心感—-。
離職防止から退職者エンゲージメントというフェーズへの一歩は、働き方改革の文脈からみても、未来を拓く一歩かもしれません。
「退職を希望する従業員とは面談します。そこで大切にしているのは、その人の人生にちゃんと寄り添って相談に乗れているかということ。退職して新たな世界を知るほうがその人のプラスになるんじゃないかと感じたら、むしろ卒業していくことに背中を押すこともあります―――」
アルムナイ制度を導入しているある飲食チェーンの人事担当役員の言葉です。
自分が取材した企業で、アルムナイ制度を導入しているところほど、こういった人への包容力を感じさせてくれました。まぁ、そういう会社だから戻ってきたくもなるんでしょうが(笑)。
ちなみに、弊社ツナグ・ソリューションズでも、ある条件を満たしている退職者に「リターンパスポート」という復職許可証を渡しています。アルムナイ制度、実はやってます。
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。