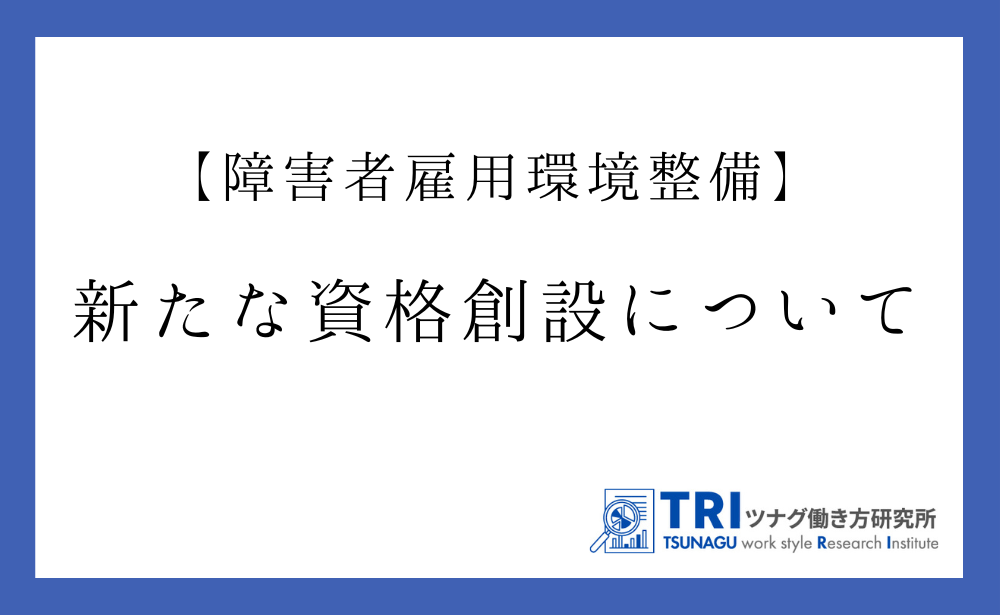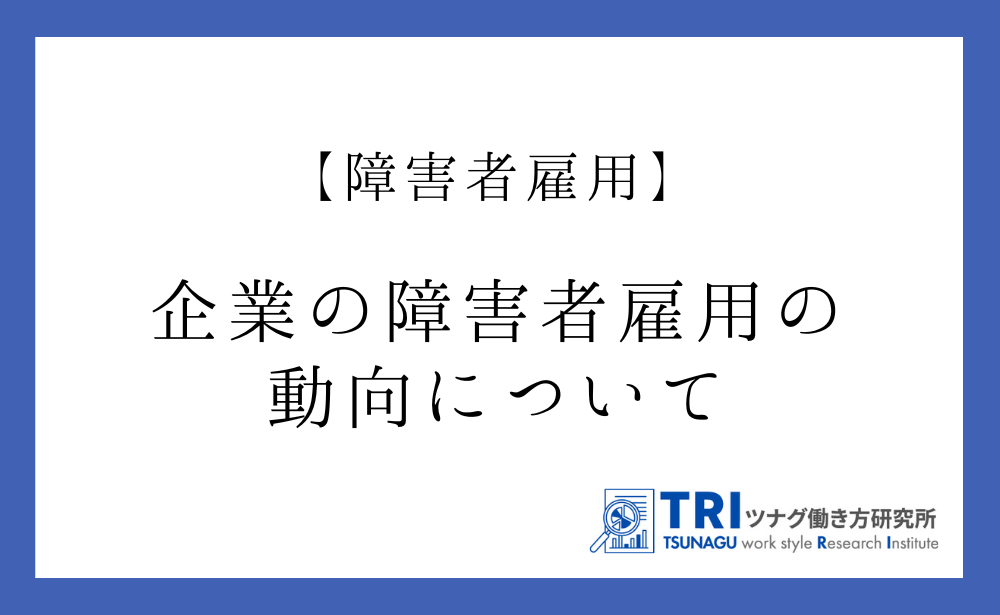News 最新情報

【障害者雇用】A型事業所の「立ち位置」について議論 苦境の施設続出、厚労省の有識者研究会
公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第7回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月25日、「就労継続支援A型事業所」について議論しました。A型事業所は、2024年度の報酬改定によって採算性が求められるようになり、厳しい運営を余儀なくされる事業所が増えています。
A型事業所は、障害者が事業所と雇用契約を結ぶ「労働者」で、法定雇用率の対象になっている一方、一般企業への「架け橋」の役割を持っているため、障害福祉サービスの報酬も支払われていることから、事業の性格をめぐって賛否が出ています。
この日も、事業経営者側からは「報酬改定で運営が厳しくなっている事業所が増えており、今後、さらに厳しくなる」「現実的な問題として、A型の“立ち位置”の変更は慎重であるべき。代わりに就労できる場が極めて限られる以上、障害者にシワ寄せの行く制度変更は好ましくない」などの意見が出ました。
一方、専門家などからは「仮に企業がA型事業所を設立すれば、特例子会社も不要になりかねない」「現在のA型事業所では社会への“架け橋”としての機能が弱く、企業で就労できる人でもA型に“留め置かれて”いる可能性もある」「A型は法定雇用率の算定対象からはずすべきだ」などの意見が出ました。
厚労省がこの日明らかにした24年度「障害者の解雇者数」によると、ハローワークが掌握した年間解雇者9312人のうち、A型事業所が8割近い7292人を占めることがわかりました。そのうち、再就職できた人は2171人だけで、雇用関係のないB型事業所への移行が3834人、求職中が856人。A型が破綻した場合、就労していた障害者の受け皿がほとんどない現実が浮き彫りになっています。
◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。