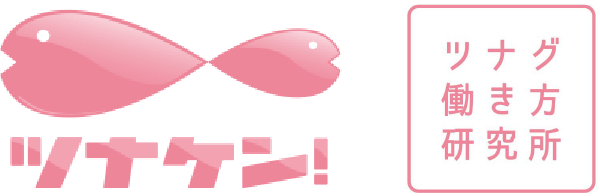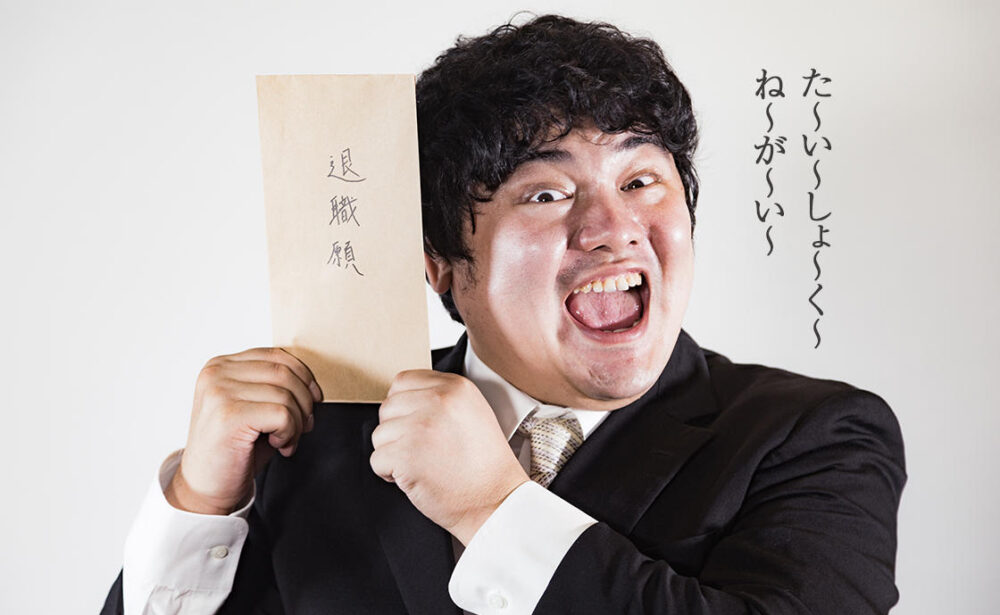【多様な働き方を研究するコラム】
ママは、本当に一回辞めちゃいけないのか
※ワークライフコンフリクトとは…
仕事上の役割と家庭や地域における役割が両立できず、対立する状況。
今回のインタビューに参加していただいたママさんたちからは
「子どもが小さいうちは子育てを優先したい。が、正社員を捨てたくない」
「仕事も育児も中途半端になるんじゃないか」
「仕事優先になることで、子どもがさみしい思いをするんじゃないか」
などなど、仕事と育児の間で揺れる赤裸々な声を聞かされました。
あるバリキャリ系のママからは、独身時代エース級の働きで将来を嘱望されていたがゆえに、復帰した職場でのポジションが歯がゆくて、でも、今、自分にできることが、このくらいしかないんだと自覚して泣いた、という声も。
また、あるママは、育休後1年で復帰する約束を会社と交わしていたのですが、1年経過後、結局復帰せずに退職するという選択をしたとのこと。なぜか。
子どもがかわいくてしかたなくて離れることができなくなったらしいのです。
現在の論調は、とにかく辞めずに休んで復帰しよう、です。
働く側と経営側の双方にアドバイスを続ける昭和女子大学の坂東真理子理事長兼学長は、
「(高速道路を降りずに)キャリアを積めば将来『見える景色』が違う。貴重な人材を失わないために企業は柔軟な働き方ができるようにし、キャリア形成の早期のうちに仕事のおもしろさややりがいを味わう機会を与えることが重要」
と指摘しています。 高速道路とはバリキャリ女性が走るキャリアの道の例えでしょうか。
国力の視点から女性活躍をみると、グローバル社会の中で日本企業がイノベーションを創造していくダイバーシティとしての文脈が優先され、そのためには辞めずに高速道路を走り続けるのが望ましいという論調も、もちろん理解はできます。
前述のバリキャリママも、悔し涙を流しなら復帰後、できることから頑張っています。彼女の頑張りが『見える景色』を変えてくれること切に願います。
でも、もう一人のママが復帰を断念したという選択は本当にダメなのでしょうか。子どもがかわいいという根源的な思いを否定できるのでしょうか。
リクルートジョブズが行った調査では、就業意向のある20~40代のママの半数近くが、保育園に子供を預けることへの抵抗感を感じていることが報告されています。
理由は、圧倒的に「親が育てた方がいいから(69.2%)」「子どもがかわいそうだから(42.7%)」(※複数回答)が中心となっています。
スイスの動物学学者アドルフ・ポルトマンが「生理的早産」という概念を唱えています。これは、本来、ヒトの赤ちゃんは、21ヶ月で誕生すべきところが、 直立歩行による骨盤の矮小化によって、胎児の身体的成長に限界がある為、大脳の発達を優先させて10ヶ月で誕生するという説です。
そもそもヒトはあと1年くらい胎内にいて生まれてくるのが自然なのだということをポルトマンは述べているのです。つまり生まれた瞬間の赤ちゃんは、地球上最弱の哺乳類であり、そんな最弱な生き物が安全に育つためにも、いちばん身近な存在であるママには、子供を愛おしく思う地球上最強の母性がプログラムされているというのです。
このような自然な気持ちに従うというのは果たして間違っているのでしょうか。
そういった文脈の中で、いくつか復帰ママにフィットした働き方が提案されてきたことは、小さくて大きな一歩かもしれません。
例えば、宅配便大手の佐川急便では、配送力強化の一環として2014年4月から主婦を活用した「宅配メイト」の全国展開を開始しました。
「宅配メイト」は自宅の周辺エリアのみを担当し、少量の荷物を配達するスタッフで、アルバイト・パートといった雇用形態は取らず、登録者と業務委託契約を結ぶ形態をとっています。
(1)ご近所で(2)短時間(3)しかも雇用という縛りなく働ける、のが主婦に支持されています。
そもそもは、主婦に向けた働き方を新設したというより、個人宅の在宅率が高い午前中の配送を強化するために、9時から12時まで働ける短時間勤務の人材を募集したところ、なんと8割が主婦層からの応募だった、という事実がきっかけでした。
このように朝方短時間シフトなら主婦の応募が集まりやすいことがわかり、そこに着目して採用を強化するようになったことから生まれた働き方なのですが、復帰ママのファーストワークにはもってこいではないでしょうか。
また、リクルートホールディングスが家事支援サービスに乗り出す、との報道がありました。人材派遣業のノウハウを生かして主婦を活用し、掃除を中心に手軽に頼めるメニューを提供するというビジネスモデルで、特徴は掃除や整理整頓、食器洗いなどの作業に絞った1回当たり2時間で税別5千円のサービスメニュー。
主婦力をいかしたマイクロタスクという点では、このサービスも復帰ママにフィットしそうです。
是が非でも辞めずに働くのではなく、一回辞めて思う存分子育てを全うしたうえでも復帰しやすい環境や仕組みを模索することも、辞めずに働く支援と同じくらい、今求められているのではないでしょうか。
ちょっとずつ一般道を走りつつ、徐々にスピードに慣れて、本人が希望すれば高速道路に復帰する、というキャリアルートが、もっとクローズアップされてもよいのではないか、と個人的には考えています。
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。