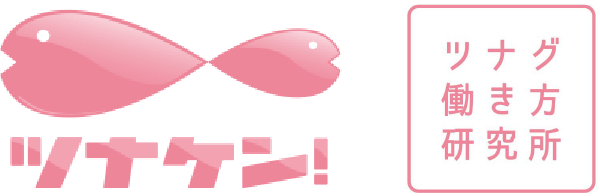【多様な働き方を研究するコラム】多様な働き方を改めて噛みしめた夜
青山のとあるワインバーを訪れました。
正確には、サザンオールスターズのアルバムタイトルにもなった「キラーストリート」と言われるオシャレなエリアの、オシャレなワインバー。お店のエントランスは、自然派ワインのショップになっていて、奥の扉を開けると、こぢんまりとした空間があり、美味しいこだわりのワインがいただけるという、まさに隠れ家的バーでした。いまや業界人となった後輩の、やや自慢気な「紹介したい穴場のワインバーがあるんです!」というお誘いを受け、今もっとも東京らしいお店のひとつといえるようなシュッとしたバーを訪問したのです。
このワインバーの食レポをするつもりは毛頭なく、気になったのは、このバーの「店長」なのです。普段は、ファッションショーの演出をしているらしいのですが、ワイン好きが高じて、自分がセレクトした自然派ワインのショップをはじめ、さらにその奥にワインバーを作ってしまったとのこと。実はモデルでもあるそうで、かなりのイケメンです。そしてカウンター越しにワインへの愛を饒舌に語るその姿は、ビジュアルだけでなく、好きなことを仕事にしている人が共通して放つカッコよさに満ちあふれているのです。
彼の場合は、このお店のオーナーであるので「店主」という呼称のほうが正確なのかもしれませんが、自らお店に立ち、ワインをサーブし、料理を作り、スタッフを指揮する、という仕事をしている点から定義すると、「店長」という存在でもあります。
どうでしょう?
一般的な店長のイメージとは、かなりかけ離れていませんか?
誤解のないように弁明しておきますが、我々ツナグ働き方研究所は「サービス業で働くヒトたちを応援していく」というミッションを掲げています。おもてなしの国と言われるニッポンにおいて、サービス業の要である店長を応援したい気持ちを強く持つ立場です。そういった意味で、逆に一般的な店長イメージを憂いているのです。
我々の実施した「アルバイト労働時間調査」では、今のアルバイトスタッフは、行きすぎたブラック報道の反動からか、労働環境が守られている傾向にあることが明らかになりました。無論、そのシワ寄せが現場責任者である店長に行っているわけです。先日取材した店長は、一カ月でなんと200時間残業しているとのことでした。そういった負のイメージが、一般的な店長像を形成していくことにつながります。飲食店や小売店でアルバイトする学生にインタビューした時に「店長にだけはなりたくない」という声が大多数を占めたのはショックでした。
先述のカレを労働学的に評価すると、今、国が推す「副業を持ち、多様な働き方を実践する」という点で、21世紀を牽引していくアイコン的な労働者といえるかもしれません。もちろんカレのようなカッコいい働き方のできる店長は稀なのでしょうが、ステレオタイプな店長イメージに拘泥されすぎることへの無意味さを気づかせてくれました。
本来ひとりひとりの価値観によって育まれる働き方こそが、多様な働き方の実践となるはずだと考えます。“働くこと”と“呼称やステイタス”とは実は大きな関わりがあって、もっと言うと、働くことが“身分を示すこと”に通じやすく、その価値観がステレオタイプな働き方を創り出し、画一化の方向にねじ曲げたりしがちです。
「多様な働き方を研究する」――――
それは、一般論的偏見や画一的価値観から「真の多様性」を解放していく果てしなき旅にほかならない! 美味しいワインをいただきながら、そんな覚悟をあらためてかみしめた夜でした。
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。