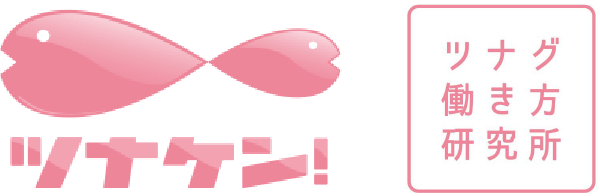【多様な働き方を研究するコラム】現場コミュ力の大切さを痛感
今回はツナグ働き方研究所所長の平賀より、このコミュニケーション力の大切さをお話しいたします。
「キャンペーンだからNO.1店舗目指して頑張ろうって言われても、ぶっちゃけ、ヤル気出ませんよね」
先日、カジュアル衣料チェーンのショップで接客販売のアルバイトをしている女子学生から話を聞く機会があり、その時の彼女の言葉です。
同じブロックの他店舗と新商品の販売成績を競うキャンペーンがあって、店長からその檄が飛んだ時の率直な感想で、「そのキャンペーンで優秀な成績を取るとその新商品の洋服がもらえたんですけど、頑張るってより欲しきゃ自分で買います、みたいな…」との発言も。彼女は、覇気のない若者というというわけでなく、むしろ普段は言葉遣いも礼儀正しい女子学生でした。聞けば、社員の業務であるレジ閉めを任されたり、ミシンでの裾上げ業務までこなすとのこと。
普段、ちゃんと働いている彼女が感じたのは、こういうことのようです。キャンペーン頑張りたいのはいい成績を上げたい店長であって、週に数回シフトで勤務する自分たちアルバイトにまで、同じ熱量を求めてきたことに共感できないと。確かにこの手のミスコミュニケーションは、パートアルバイトスタッフを多く抱えるダイバーシティの職場にありがちかもしれません。
せっかく雇ったアルバイトがすぐに辞めてしまう。その一番の理由は、事前に聞いていたよりも仕事が厳しかったり、想像と違っていたりすることです。いや、面接で厳しいと伝えているし、本人もわかりましたと答える。厳しいことは納得しているはずなのに……と思う採用担当者は少なくないでしょう。
しかし、企業の言う「厳しい」と応募者の受けとめる「厳しい」には、大きな温度差があったりします。企業側は業績を上げるため毎日必死です。アルバイトに対しても「早く一人前になってほしい」と高い要求をしがち。一方、特に学生のアルバイトなどは社会経験がほぼないため、事前に「厳しい」と聞かされていても、その度合いがわかりません。アルバイトの立場である自分が、難易度の高い仕事を任されたり、成績を競わされたりするなど、想像していない場合がほとんどでしょう。
このような温度差は、特にコスト圧縮で人員に余裕がない、また社員を極限まで削減しアルバイトに依存する企業や店舗が増えてきた昨今、どんどん拡大していると思われます。
そういった温度差を埋めて、ダイバーシティの職場を活性化する、多様な働き手のヤル気を刺激するには、どうすればいいのか。ずばり現場責任者がコミュニケーションの距離感をうまくとっていくことが重要です。ただでさえ、ちょっと残業をお願いするとブラックの汚名を着せられたり、褒めたつもりがセクハラと勘違いされたり、なにかと難しくなっている職場でのコミュニケーションですが、一方、積極的なコミュニケーションを求める声もあります。求人大手インテリジェンス社が運営する「anレポート」の調査では、「店長が飲み会に誘ってくれるのは、あり?」のアンケートでは「あり派」が90%で、「仕事仲間との交流を深めるためにも飲み会は必要」という声が多く見られました。
また「店長がダジャレやおやじギャグを言うのは、あり?」のアンケートでも「あり派」が87%にもなり、「ダジャレ言えるぐらい気さくな人のほうが仕事しやすい」と前向きな声が多く見られており、明るい雰囲気づくりの一環として受け入れられることが分かりました。
前出の女子学生も、「同じ目標に向かって頑張ろうというような熱苦しいコミュニケーションはひく。むしろストレートに、店長の自分がイチバンとりたいんだよね!協力してくれないかな!くらいのほうが、手伝ってあげようかなという気になる」と。飾らないコミュニケーションがイチバンかもしれませんね。それがまた難しいのですが。。。
◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。