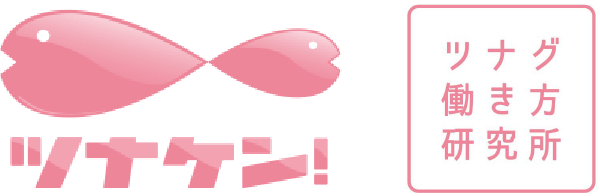【店長応援企画・店長のミカタ】
個のトレーニング状況や組織の課題をリアルタイムに可視化
ピーシーフェーズ中村昌広さん
おもてなしの国ニッポン。その世界最高峰のサービス力を支えるのは、間違いなく現場を仕切る店長だ。飲食業界を牽引する主役たちを、どのように支援していくのか。その大きなイシューとして、店長の業務負荷軽減がある。
店長業務の中でも大きな割合を占めるのが「人」の問題。中でも人材育成は、従業員の戦力化による店舗生産性の向上、また定着による店長の物理的負荷軽減を促すという意味で、極めて重要なタスクとなる。
今回は、従業員の教育、育成に特化したマイクロラーニングシステムのサービスをご紹介しよう。ピーシーフェーズが運営する「shouin」は、スマホ動画を駆使したマイクロラーニングシステムを提供する。時代にマッチしたプロダクトで効率的な学習ができるだけでなく、業務習熟度の可視化や評価とも連動した教育育成支援サービスだ。サービス開発時からプロジェクトに関わる中村昌広さんに、詳しくお話を伺った。
店長業務の中でも大きな割合を占めるのが「人」の問題。中でも人材育成は、従業員の戦力化による店舗生産性の向上、また定着による店長の物理的負荷軽減を促すという意味で、極めて重要なタスクとなる。
今回は、従業員の教育、育成に特化したマイクロラーニングシステムのサービスをご紹介しよう。ピーシーフェーズが運営する「shouin」は、スマホ動画を駆使したマイクロラーニングシステムを提供する。時代にマッチしたプロダクトで効率的な学習ができるだけでなく、業務習熟度の可視化や評価とも連動した教育育成支援サービスだ。サービス開発時からプロジェクトに関わる中村昌広さんに、詳しくお話を伺った。
売上の良い店舗ほど「教育に力を入れている」

- 平賀
- 「第16回 日本e-Learning大賞」のナレッジシェア特別部門賞受賞、おめでとうございます。ちなみに「shouin」というネーミングは、かの吉田松陰から取ったんですよね。
- 中村
- そうなんです。彼は、明治維新の原動力となる数多くの逸材を輩出した教育者でしたから。
- 平賀
- なるほど。歴史に名を残す教育者にあやかったわけですね。改めてサービスを立ち上げた経緯を教えてください。
- 中村
- われわれは企業や店舗の課題に向き合いながら、さまざまなシステム開発に携わってきました。それこそ一日体験じゃないですけど、店舗のキッチンで働いてみるとか、現場をじっくり観察した上で、課題解決のお手伝いをしてきたんです。そこで、「売上が良い店舗」と「ダメな店舗」を大きく分ける要因があると気付いたんです。売上の良い店舗の店長さんに話を聞くと、だいたい「教育に力を入れている」と。「入ってきたスタッフをきちんとケアする」という店長が非常に多かったんです。
- 平賀
- 経験則から、教育、育成の重要性を捉えていたんですね。
- 中村
- そうですね。平賀さんの著書も読ませていただきましたが、そこに書かれていたように、採用段階でコストを掛けても、定着率を高めないと、まさに穴の空いたバケツで延々と水をくみ続けるようなものです。
- 平賀
- 採用して、その後、軌道に乗るまでのケアこそが大切ですからね。
- 中村
- 本当にそう思います。
- 平賀
- そこでスタッフ育成支援のプラットフォームを作ろうということになったんですね。システムや機能としてこだわったのは?
- 中村
- 今までのラーニングシステムは、PC主体だったんですよね。shouinは完璧にモバイルファースト。ユーザーのことを考えて、全部スマホの端末で見やすいように設計しようと。ただ、会社事情によっては、利用できる端末も違ってくるのでタブレットやPCでも閲覧することができます。
- 平賀
- サービスの内容としては?
- 中村
- どういう進捗で進んでいるかがすぐに分かって、まだ見ていない動画は何なのかというのが、分かりやすく可視化されるものにしようと思いました。自分自身が「今どの状態なのか」を把握して、「次はこれ」というように学習を習慣化するよう にさせることを意識しています。

1本の動画は30秒〜1分隙間時間で効率的に学習できる

- 平賀
- 現在はやはり、新入社員や新人スタッフ向けに使われる企業さんが多いですか?
- 中村
- そうですね。あと、とあるアパレル企業さんなどは、内定者向けのコンテンツとして、入社前の教育に導入されている場合もあります。だいたい入社3カ月くらいまでの方向けに導入される企業が多いです。
- 平賀
- 企業によっても違うと思いますが、ラーニングのためのコンテンツは、だいたいどれくらい用意しているものなんですか?
- 中村
- 本当にまちまちですが、多いところで200〜300本。平均で50〜60本くらいでしょうか。どんどん追加されていく企業もありますし、内容の変更が必要になる場合もありますよね。なのでスマホで簡単にアップロードをしやすいように設計しました。学習すべき内容も、日々改善、更新していくものですから。
- 平賀
- 動画は販売業や飲食業ではベーシックな接客の仕方などがメインになってくるんでしょうか。
- 中村
- そうですね。おじぎの角度とか、一口に「笑顔」と言っても、3分咲き、5分咲きなど、どれくらいの「笑顔」がふさわしいのかというのも、動画でならイメージがつかみやすいですよね。あとは商品の提供の仕方や配列の仕方など、直感的に理解しやすくなっていると思います。
- 平賀
- 動画1本の長さってどれくらいなんですか?
- 中村
- 短いですよ(笑)。30秒〜1分です。推奨しているのはそれくらいの長さです。録画したものが5分を超えても、編集でカットして1分にしましょうと。
- 平賀
- 経営理念を伝える動画なんかは、その限りではないんでしょうけど(笑)。
- 中村
- そうですね。社長さんの言葉なんかは、どうしても切れないところもあるので(笑)。でも基本は、隙間時間に見てもらう動画なので、できるだけ要点だけを短く伝えるようにしています。
- 平賀
- 隙間時間とは?
- 中村
- 休憩中とか入店前の時間です。この5分や10分でいかに効率的に大事なことを学んでいけるか。
- 平賀
- なるほど。それだと学習負荷も大きくないですしね。

「学習」が「評価」につながるラーニングシステムの仕組み

- 平賀
- 学習のモチベーションを上げるためには「評価」という部分も重要だと思いますが。
- 中村
- そうなんです。さまざまな企業を見てきた中で、「評価」という軸は、スタッフの育成と離せないものだなと。目標としてのゴールがなければ、学習する必要を感じてもらえませんから。shouinでは「スター評価」と呼んでいるんですが、今自分がどれだけのことを学んでいて、それが実際に育成担当や人事からどのような評価を得ているのか、スマホ上で確認できる。このシステムの大きな特徴といえるかもしれません。
- 平賀
- 具体的には、動画での学びをどのように、「評価」につなげていっているのですか?
- 中村
- スタッフが動画を見て学んで、「これは学んだ」というものにはチェックをしていくんです。それが通知で教育担当や店長さんに共有されるので、今度はその実践の場面で、本当にそれが「できているか」を抜き打ちじゃないですけど、リアルな現場で確認します。それができていれば「スター評価」につながりますし、できていないと感じたら再度学習の必要があると差し戻します。それを見てそのスタッフは「次はこれができるようにならなければ」という目標の設定もしていけます。
- 平賀
- スタッフそれぞれが「今何ができて、何ができていないのか」がきちんと分かるシステムになってるということですね。まさに「状態が分かる」という。
- 中村
- そうなんです。先ほども言いましたが、優秀な店長は、スタッフのコンディションをよく見ているんです。だから、shouinは、そのエッセンスを受け継がせていただき、「スタッフの状態を見える化したい」にこだわっているんです。
- 平賀
- 非常にいいなと思うのは、全てがシステム任せではなく、一番大事な「評価」の部分には、必ず店長なり人事担当なりの、人間の目が入るところですね。サービスベンダーの方の考え方にもいろいろあって、一つのシステムで全て自動化して完結できるのが良いとされる場合もありますよね。でも、中村さんが人間のリアルなコミュニケーションを生かしたいと考えるのはどういう理由からですか?
- 中村
- システムだけで完結するサービスは、導入目的は「ラクになるから」という部分が大きいですし、もちろんそこはshouinも、店長や担当者を煩雑な仕事からできるだけ解放してあげたいという思いでやっているものでもあります。ただ、人材育成のためのサービスは、そこだけではいけないと思うんです。
- 平賀
- なるほど。
- 中村
- 学びが進んでいくごとに、そこで会話が生まれてほしいんですよ。コミュニケーションがなくなれば、孤立して辞めてしまう人も増えます。世間話でも何でもよくて、システムはそれにつながるきっかけになってほしいという思いがありますね。
- 平賀
- まったく同感です。
- 中村
- 育成って、僕自身もそうですけど、メンバーと話すのも仕事のうちだと思うし、「状態を見る」っていうのはとても重要な仕事で、システム上では見えない評価も必要です。リアルなコミュニケーションこそが「辞めない」という定着につながるものでもあると、僕らはいろいろな店舗を見てきた中で実感したので、そこは手放したくないですね。

アルバイターとしての評価を次の就職にも活かせるような未来を
- 平賀
- 飲食業で、面白い使い方のエピソードがあれば教えてください。
- 中村
- 100店舗ほど運営している会社の事例を紹介します。通常のラーニングコンテンツは充実しているんですが、プラスアルファのユニークな使い方をされています。ある店舗の売上トップの店員さんが「僕はこういう接客をしています」という動画をアップしてシェアしてるんですよね。アルバイター発信で動画を上げてるんです。同世代のスタッフには共感するところも多いみたいで、「私にもできるんじゃないか」とか、まねできないまでも参考にしたり。
- 平賀
- 面白いですね。やはり若い人たちはもう動画をアップすること自体にハードルは感じてないですよね。
- 中村
- そうなんです。自分たちで録画して編集も簡単にやりますからね。それでスタッフ同士の横軸のコミュニケーションも活性化したりして、こちらが想定していない使い方ではあったんですが、shouinの使い方の可能性はまだまだたくさんあるんだなあと感じました。
- 平賀
- アルバイターさん主導でそうしたコミュニケーションが生まれるというのも良い話ですね。
- 中村
- はい。shouin自体も、正社員はもちろんですが、今後はもっとアルバイターさんにフォーカスするようなサービスにしていきたいと考えているところです。アルバイトとしての経験や評価が、次に働く企業でも「評価」として認めてもらえるようになるとか。面接のときに、前職での評価をアピールできるような仕組みというか。学生のアルバイトでも、この子はこれだけの評価を得ているので次の就職にも有利になる ように、何らかのスコアがオープンにできるようになったらといいなあと思っています。もちろんさまざまな課題はあると思いますけどね。
- 平賀
- 活躍人材としてのバッジがもらえるみたいな感じですよね。
- 中村
- そうですね。そうすればモチベーションも高まるでしょうし、何か、これまでの評価が形になるような仕組みを、今は考えています。
- 平賀
- 今後もshouinはアップデートを繰り返していくと思うのですが、次の課題というか、何か考えていることはありますか?
- 中村
- 現状のサービスでは、「今ここまでできるようになった」という把握までなんですが、2020年には「シナリオ」として、「この動画を見たら次はこちら」とか、「次はこのクイズにチャレンジ」というように、ネクストステップを提示していけるような設計に更新していく予定です。あと、実際の人事評価に連携するような仕組みも考えています。
- 平賀
- 実際の昇給や時給アップに連動するような仕組みですか?
- 中村
- そうですね。現段階ではshouin上でしか評価が見られないので、それを人事とひも付けて評価していくというのが、次のフェーズかなと考えています。
- 平賀
- 結局「適正な評価」がスタッフの一番のモチベーションですもんね。その可視化をシステム上で推し進めていくのは非常に正しい気がします。それがあってこそ、教育や育成が機能し、「定着」につながるんだと思います。本日はありがとうございました。
* * *
今、「オンボーディング」というキーワードが話題だ。組織に新しく加わった人材を1日も早く戦力化し、組織全体との調和を図ることを目的とした育成プログラムを指すが、その整備はまさに時代の要請といえる。このshouinは、その育成プログラムの実行を支援するという意味において、まさに時代の芯を食ったサービスだといえる。
そして、事例として挙げていただいた飲食店でのアルバイターの動画投稿。これは、まさに吉田松陰が説いた「師弟同行」ではないか。勉学を共にする仲間に対してもお互いを師と呼び教え合うという「共学」の思想が、図らずも実践されている。
命名者もガッツポーズしたに違いない(笑)。
◆プロフィール

中村昌広(なかむらまさひろ)
ピーシーフェーズ株式会社
shouin事業本部マーケティング&セールス部部長
◆本件に関するお問い合わせ先
ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。