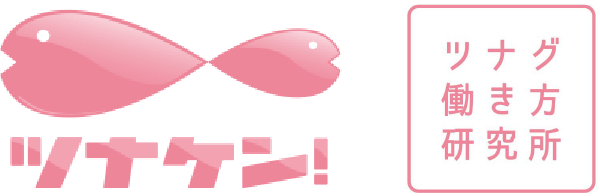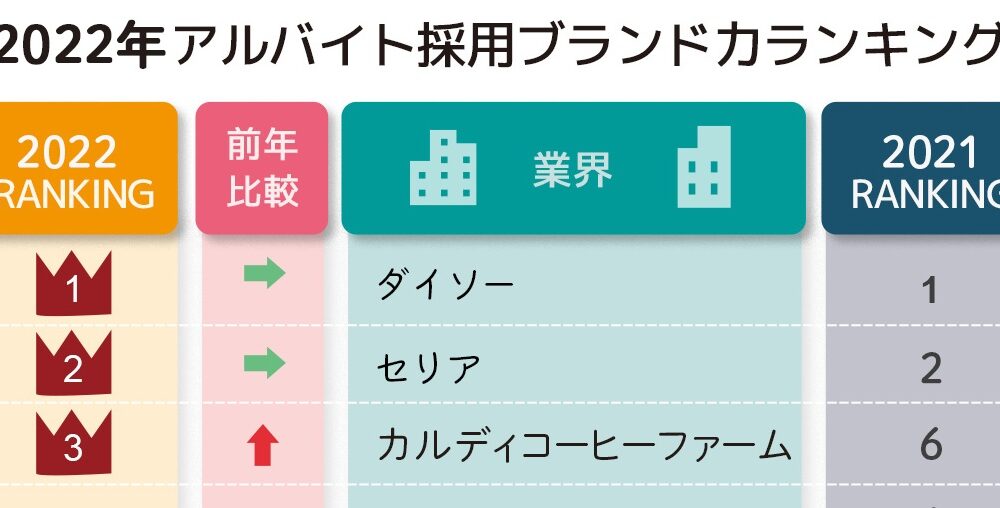【多様な働き方を研究するコラム】令和のリーダー像が鮮明になった日
第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、侍ジャパンが劇的な優勝を果たしてから一か月がたちました。WBC戦士たちは連日のようにマスコミに取り上げられ、功績の記憶が薄れることはありません。中でも引っ張りだこなのが栗山監督です。14年ぶりの王座奪還に導いた手腕を称賛する声が、日に日に高まっているように思います。
さて、今回の大会で、栗山監督はどのようなリーダーシップを発揮していたのか。いたるところですでに語られているテーマではありますが、組織開発の視点から改めて整理してみましょう。
栗山監督が志向し実践したのは、
「トップダウン的なリーダーシップではなく、選手とのコミュニケーションや関係性を大切にし、選手の個性を活かしながら主体性を引き出すことで成果を導く」というリーダーシップでした。
実はこれ、組織論のセオリーとして近年注目を集める「サーバントリーダーシップ」そのものといえます。「サーバント」とは、「使用人」「召使い」という意味。奉仕の気持ちを持って接し、どうすれば組織のメンバーの持つ力を最大限に発揮できるのかを考え、その環境づくりに邁進するリーダーシップと定義されています。
召使いという語感はさておき、この定義を聞くと、栗山監督が実践した手法と合致しているのがお分かりになるでしょう。
栗山監督がどのようにサーバントリーダーシップを発揮しているのか。非常に分かりやすい具体的事例をいくつかあげて振り返ってみましょう。
まず思い浮かぶのが選手との関係性のポジショニングです。栗山監督のコミュニケーションのニュアンスには、『監督と選手』という上下関係よりも、対等なパートナーシップを築こうとする雰囲気があります。特徴的なのが選手の呼び方。例えば大谷翔平選手を「翔平」、村上宗隆選手を「ムネ」と呼ぶことで、フラットな距離感をつくっていました。
繰り返しになりますが、サーバントリーダーシップとは、「召使い」のような奉仕のスタンスがベースです。上から目線ではなく対等に接することでフランクな関係性を作るのはサーバントリーダーシップの第一歩。これが、選手達のチーム内における心理的安全性を高め、プレイに集中できる環境ができた一因であるのは間違いありません。
そして、栗山監督の真骨頂といえば「選手を活かす、信じること」です。これは各方面でも取り上げられていますが、まさに栗山監督がサーバントリーダーシップの体現者たる最大のポイントです
これは今回のWBCだけではありません。日本ハムの監督時代から「選手を活かす」ことへのこだわりは、多く見られました。その代表的な事例は大谷翔平選手の二刀流です。数々の批判を押しのけ、大谷選手のポテンシャルを信じぬき二刀流を成就させました。
今回、村上選手の起用法に関してはWBC開催中も、「変えたほうが良い」「打てないのだから、送りバントをさせるべきだ」といった声が多い中、栗山監督は一貫して村上選手を変えませんでした、結果としてメキシコ戦のサヨナラ打やアメリカ戦のホームランに繋がったのはご存じのとおりです。
しかし、これ、なかなか真似できるものではありません。あの場面で村上選手が凡打をして敗退していたら、栗山監督は世の中から大非難を受けるのは間違いありません。
ビジネス界に置き換えて考えてみても、どうしても部下の一挙手一投足が気になり、「信頼」よりも「心配」のほうが先に立って、細かいところまで指示命令する「マイクロマネジメント」になりがちです。
しかし、「信頼されて任される」のと「細かいところを指摘ばかりされる」のとでは、メンバーのやる気も大きく変わります。メンバーの力を信じて引き出すことで重要であることを、改めて栗山監督は示してくれました。
そして、こうした「サーバントリーダーシップ」を実践しているのは、実は栗山監督だけではありません。昨年末のサッカーワールドカップの森保監督しかり、近年、箱根駅伝で優勝常連校なった青山学院大学の原監督しかり。
共通するのは、メンバーの輝きと成長をテコにチームの生産性を最大化するリーダーシップであること。これがチームビルディングにおいて有効だというエビデンスが、原監督や森保監督によって示され、今回の栗山監督によって確証を得たのです。
長らく日本において主流だったのは、その対極にある「支配的リーダーシップ」でした。リーダー自身の考え方や価値観を貫き、部下を強い統率力で引っ張って行く「強いリーダー」が幅を利かせていました。
しかしサーバントリーダーシップの有用性が明らかになり、具体的な実践手法の解像度がここまで上がった今となっては、我々も頑張るしかありませんね。簡単ではないにせよ。
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。